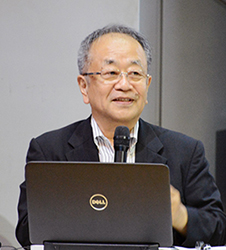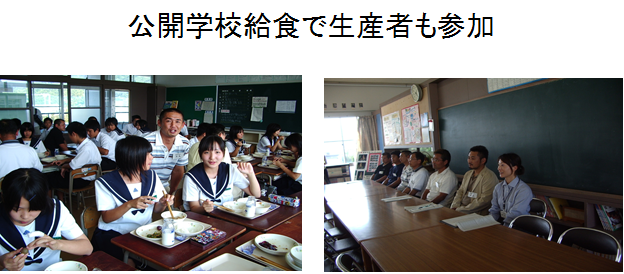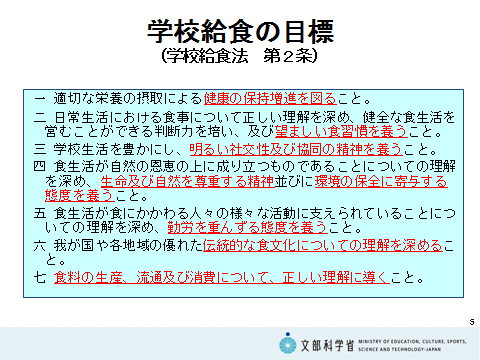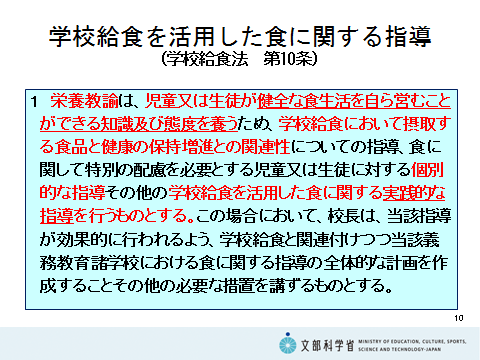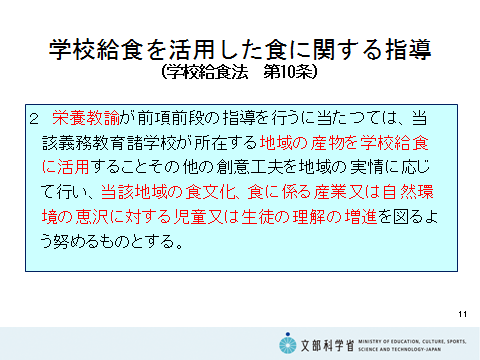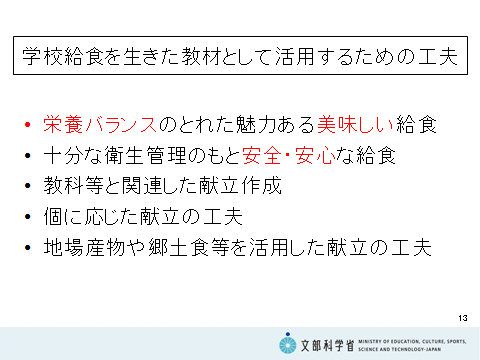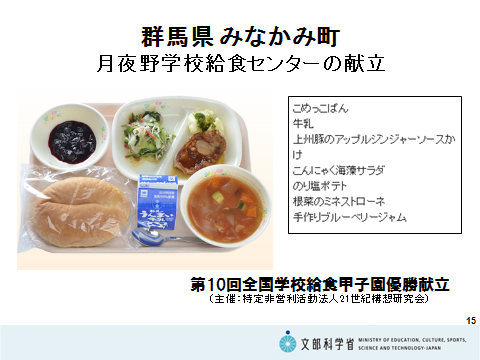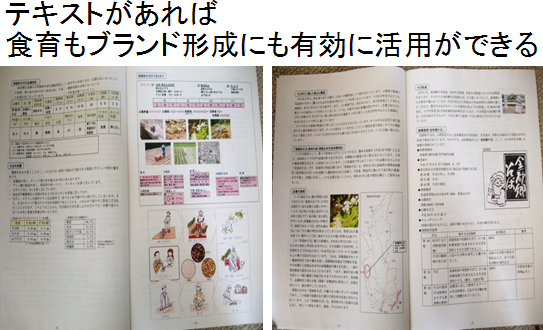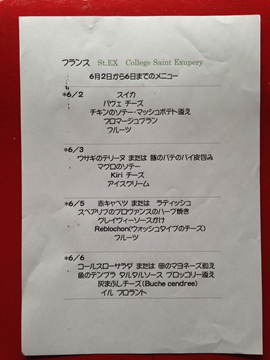2015年9月19日の戦争法の強行採決から1年を迎える。伊藤先生は、あの暴挙を機会に憲法を学ぼうと呼びかけて講演が始まった。
「私たちは誰もが政治や憲法に無関心ではいられても、無関係ではいられない」と言う名言を吐き、憲法を学ぶ意義を次のように整理した。
1 憲法を使いこなして自分らしく生きる力を身につけるため(自分が幸せになるために)
2 社会のメンバーとしての役割を果たすため(社会をよりよくするために)
3 憲法改正国民投票や選挙のときに、自分の考えでしっかりと判断できる力をつけるため(未来を灰色にしないために)
続いて近代日本の歩みとして明治から先の太平洋戦争終結までの時代に憲法と国民はどのように移り変わったかを解説した。
終戦までの日本国民に人権はなく、すべて天皇ため国家のために自己犠牲することが価値あることと位置付けられていた。それは軍備拡張、富国強兵、経済発展、国家優先という思想を実現するため、国民を誘導して利用するためだった。
戦前のドイツと日本の共通点も解説した。ドイツではナチズムによって個人は民族の中に埋没し、個人と国家の区別、対立関係自体が消滅し、国家権力を制限する憲法も必要なくなった。
一方、日本では国体思想の下、世界恐慌後、軍部のプロパガンダに乗せられ、閉塞した政治や社会の変革者として軍部を圧倒的に支持したのは、貧困にあえぐ大衆であった。
国家から個人へ変わった戦後憲法
戦後、明治憲法から日本国憲法へと変わり、国家・天皇を大切にすることから個人を大切にする憲法へと変わった。国民主権、戦争できない国、差別のない国、福祉を充実させる国、地方自治を保障する国、個人のための国家へと価値観を180度切った。
日本国憲法は「人々が個人として尊重されるために、最高法規としての憲法が、国家権力を制限し、人権保障をはかるという立憲主義の理念を基盤としている」
と語り、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義を基本原理としているとした。
そしてそれは、憲法前文に凝縮された文言として存在し、国民の行動規範も示されていると語った。
ここで伊藤先生は、ドイツのナチス政権の台頭とヒットラーの思想戦略について具体的な例を挙げながら解説した。
聞いていて思ったことは、人間の心、考えていることをある恣意的な戦略によって簡単に変えて行くことができることに改めて驚いた。
と同時に、人間の心の強さと弱さが表裏一体の関係で存在することも知った。
伊藤先生は、憲法の必要性を次のように定義した。
多数意見が常に正しいわけではない。だから多数意見にも歯止めが必要である。多数意見でも奪えない価値があるはずだ。これを予め決めておくのが憲法であると。
そして政治家は人間なので誰でも自分勝手に権力を行使してしまう危険がある。だから、政治を憲法で縛っておかなければならない。これが立憲主義であると語った。
戦争放棄を目的として立憲主義
憲法は文化・歴史・伝統・宗教からは中立であるべきという視点にも眼を開かされた。憲法とは、国家権力を制限して国民の権利・自由を守る法であり、近代国家の共通として「あくまでも人権保障が目的」となっているという。
さらに日本国憲法は、戦争放棄を目的としていることに日本の立憲主義の特長が出ている。安倍内閣は、勝手にそれを無視して自分の思うとおりの政治を進めようとしているのではないか。
また伊藤先生は、個人の尊重と幸福追求権として憲法13条にある「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」をあげた。
これは「誰にも価値があり、幸せになる権利を持つということだ。自分の幸せは自分で決める(自己決定権)ものであり、「自分が幸せになれる国づくりのために選挙に行く」と語った。
日本国憲法は誰もが知るように第9条で交戦権を認めていない。だから自衛隊には交戦権がなく、海外で敵の殺傷ができない部隊であり、法的には通常の軍隊とはいえない。
これに対し集団的自衛権は「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を,自国が直接攻撃されていないにもかかわらず,実力をもって阻止する権利」としていた。(1981年5月29日,政府答弁)
ところが安倍政権は、閣議決定の解釈変更で「他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること」として、自衛の措置として海外での武力行使容認のためにはときの政府が総合的に判断できるように変えてしまった。
さらに自民党の改憲草案をみると問題点が散見していることを指摘した。集団的自衛権を容認して国防軍を創設することにより日米同盟を強化し、米国の期待に応えたいという。これは軍事力による国際貢献をしたいということと同義語である。
「個人の尊重」よりも、軍事的経済的に「強い国」づくりをしようという思想は、戦前回帰・富国強兵政策への回帰である。
さらに問題なのは、第21条(表現の自由)である。
1項 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、保障する。
2項 前項の規定にかかわらず、公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない。
第2項によって、事実上、表現の自由はなくなり、中国憲法と同じになる。
伊藤先生は「日本はどんな国に変わろうとしているのか。私たち自身が何をめざすかを考えなければならない」として「改憲の必要性が本当にあるのか。憲法は魔法の杖ではない。慎重すぎるくらいがちょうどいいのである。自分の生活がどう変わるかへの想像力を働かせることも重要だ。10年後、20年後への想像力、そして歴史を学ぶ勇気と誇りをもとう」と語りかけた。
そして最後に次のスライドを見せて私たちの行動力に期待をかけた。